- ホーム>
- 制作者について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- 堤派|大江山図座敷幟
堤派(堤等琳門人)|大江山図座敷幟
——幕末~明治期に描かれた室内用の節句幟
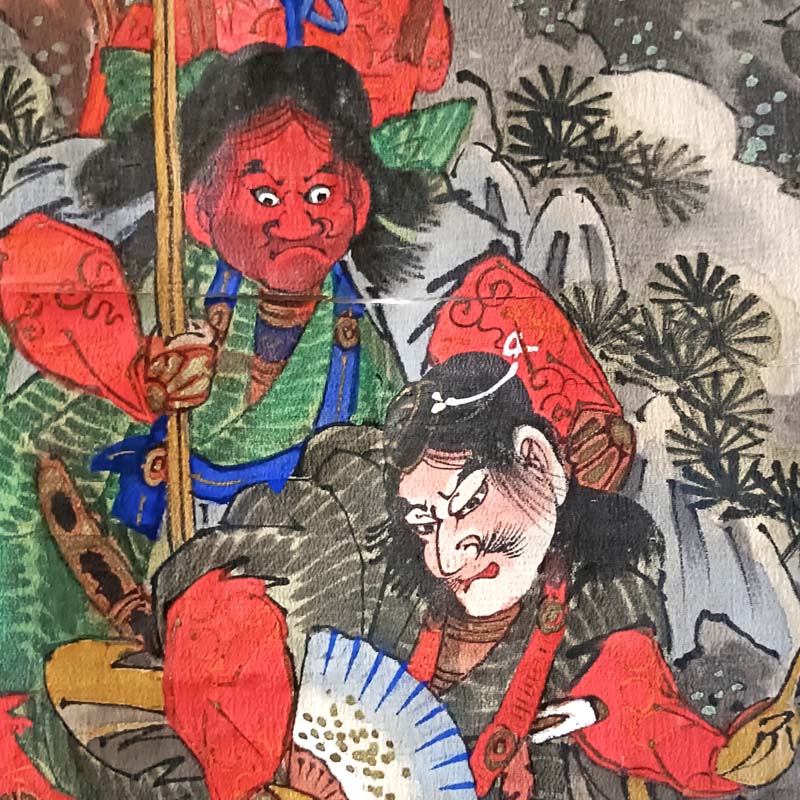
堤派と町人文化に根ざした絵のぼり

- 題名:大江山図 ※非売品
- 時代:幕末~明治初期
- 産地:関東
- 作者:堤派(堤等琳の弟子)
- 素材:縮緬
- 技法:肉筆(手描き)
- 寸法:約104×約27cm
- 所蔵:いわき絵のぼり吉田
—— 本作は、町絵師・堤等琳の流れを汲む「堤派」絵師の作品です。
彼らは節句幟のほか、絵馬や社寺の天井画など民間の需要に広く応え、町人文化の担い手として活動しました。
堤等琳は上質な仕事が好景気を背景に受け入れられ、多くの弟子を抱えたことでも知られています。
北斎との交流と影響
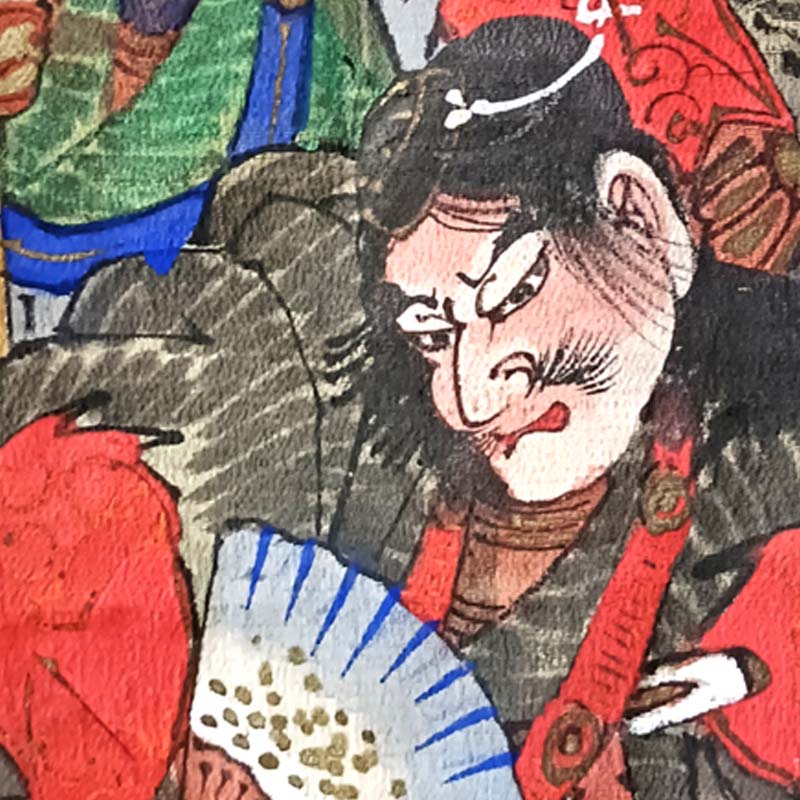
—— 葛飾北斎は一時、堤等琳のもとに弟子入りし、同居したと伝わります。
さらに弟子と北斎の娘・お栄との婚姻もあり、両者の交流は深いものでした。
北斎が「朱鍾馗図幟」(ボストン美術館蔵)をはじめとして、節句幟を手掛けた背景には、堤派の影響が関与していた可能性があります。
源頼光と坂田公時の大江山退治

—— この幟には、源頼光と四天王の一人・坂田公時が、大江山の酒呑童子討伐へと向かう場面が描かれています。
坂田公時とは、金太郎が成長して武士となった姿であり、その武勇にあやかり男児の成長を願う意味が込められました。
座敷幟という風習
—— 本作は、三幅対のうちの一つでした。
これらは屋外ではなく室内に飾る「座敷幟(内幟)」で、江戸中後期以降に定着した風習です。
また浮世絵師・歌川国貞による版画「座敷幟」と共通する場面も描かれており、当時人気の画題であったことがうかがえます。
いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)
他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧下さい
- ホーム>
- 職人について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- 堤派|大江山図座敷幟
バナースペース
 SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):
「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」





