- ホーム>
- 職人について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- 無銘|三番叟図幟
無銘|三番叟図幟(さんばそうずのぼり)
——江戸後期の節句と地域信仰を映す図像
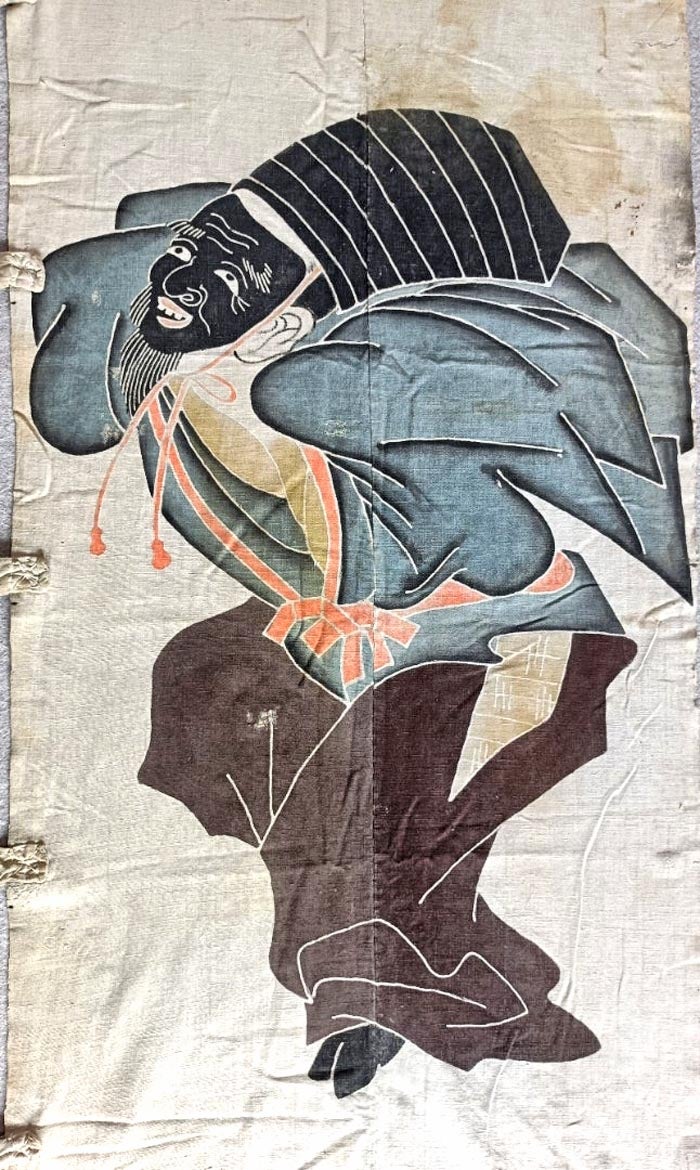
所蔵品「三番叟図幟」について

- 題名:三番叟図幟 ※非売品
- 時代:江戸後期
- 産地:不詳
- 技法:筒描
- 素材:木綿
- 寸法:約370×約68cm
- 作者:無銘
- 所蔵:いわき絵のぼり吉田
—— 白く染め残した筒描の輪郭線と大胆な面取りで、能の祝言曲「三番叟」を生気豊かに表現。
正月の印象が強い三番叟ですが、江戸期には端午の節句にも掲げられた吉祥の演目でした。
類似作:メトロポリタン美術館所蔵「三番叟図幟」

- 題名:三番叟図幟
- 時代:文政10年(1827年)
- 技法:筒描
- 素材:木綿・麻(推定)・竹・紙
- 寸法:約858.5×69.9cm
- 備考:日本の正八幡宮で使用された祭礼幟
- Gift of John B. Elliott through the Mercer Trust, 1999 / Object Number: 1999.247.6
—— たいへん興味深い事に、海を隔てたメトロポリタン美術館に、私の所蔵品と同系統の「三番叟図幟」が収蔵されていることに気が付きました。
両作品の比較から見えるもの

—— 二作の三番叟は、構図や面の形、配色は同一系統の図像感覚を示しますが、筆勢や密度には差異があります。
これは、神社の祭礼幟(格式志向)と個人宅の節句幟(実用志向)という用途・予算の違いが反映された結果なのかもしれません。
※比較画像では、私的所蔵品(右)の視認性向上のため退色補正を実施。メトロポリタン蔵(左)は無加工です。
一つの推論——神社から氏子へ、図像はどう広がったか
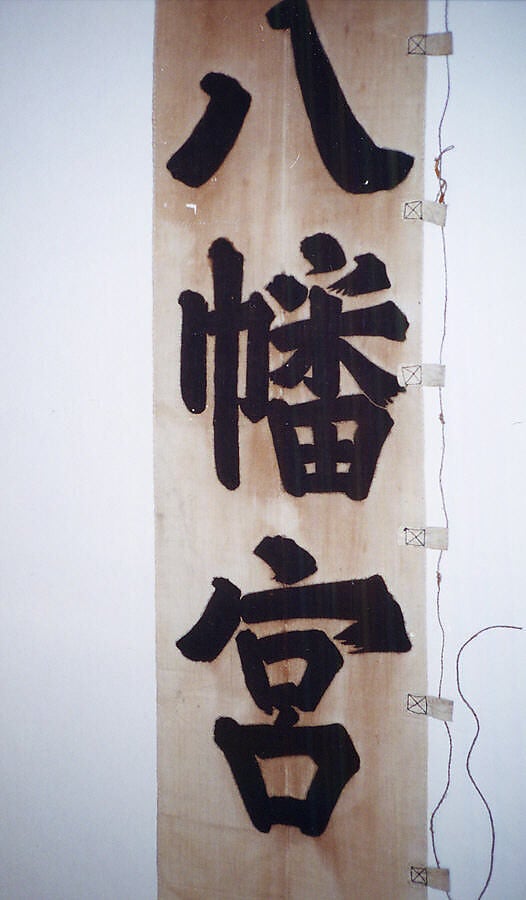
—— 正八幡宮で掲げられた三番叟幟が評判となり、節句幟にも同図様を求める動きが生じた——。
上記は一つの推測ですが、初節句を神さまにあやかりたいという気持ちから、このような同系の意匠が地域へと広がったのかもしれません。
江戸時代の絵のぼりにも「流行」があった
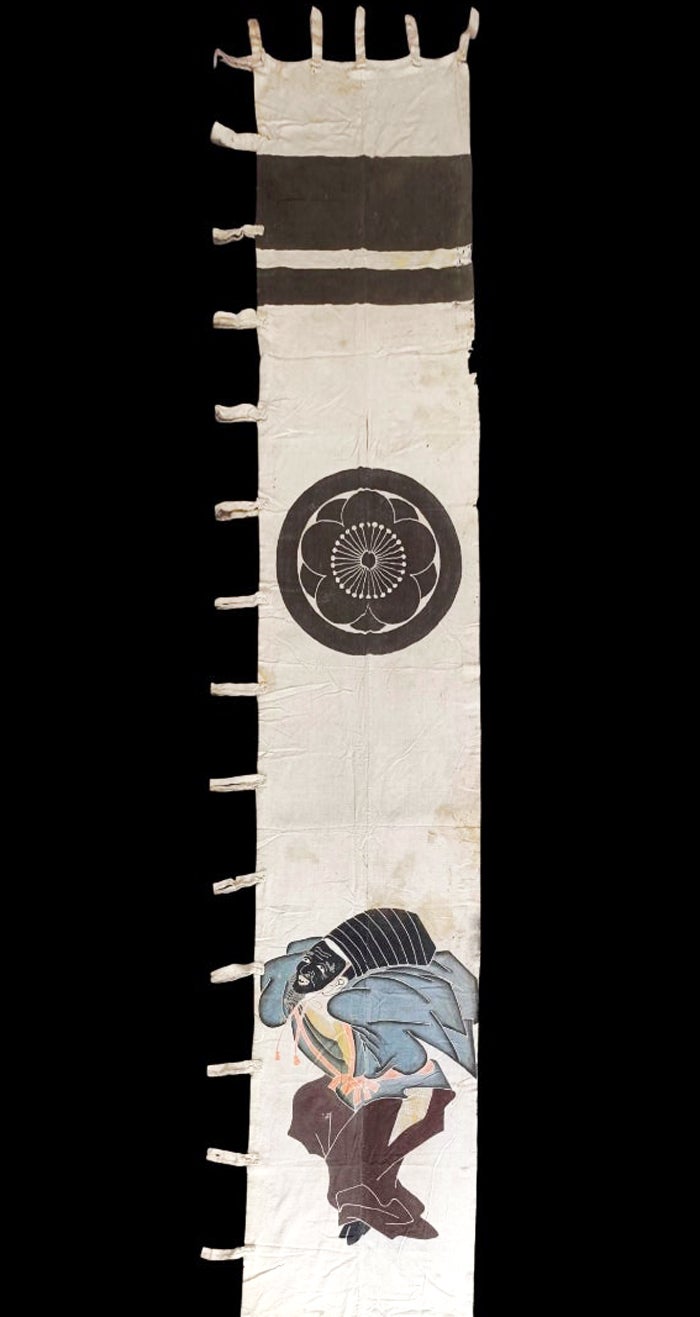
—— 図像の一致は地域的な流行の存在を物語ります。
神社中心の地域文化が、やがて個々の節句祝いへ広がる——その過程が、布上の絵に刻まれているのかもしれません。
終わりに——図像解釈に命を吹き込む


—— 保存状態差を踏まえつつ、両作の配色・省略の度合いを読み解くことは、
所蔵元・用途・制作体制を推測する手掛かりとなります。
現代の作り手として、収集と研究を通じ、伝統図像の再発見と再解釈を続けてまいります。
いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)
他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧ください
- ホーム>
- 職人について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- 無銘|三番叟図幟
バナースペース
 SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):
「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」





