- ホーム>
- 職人について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- 無銘|鍾馗図幟
無銘|鍾馗図幟(江戸後期)
——「実用絵画」としての絵のぼり/文化の地層をいまに読み解く
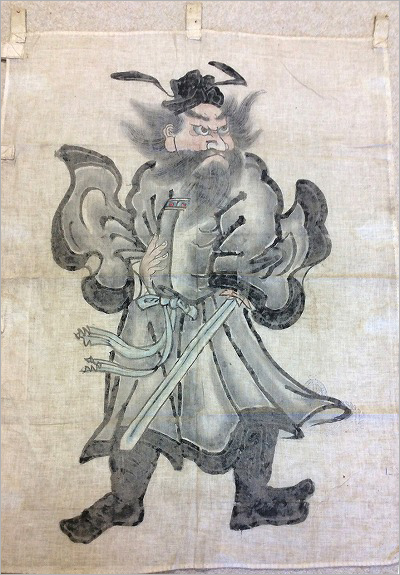
作品データ(基本情報)
- 題名:鍾馗図幟 ※非売品
- 時代:江戸後期
- 産地:不明
- 作者:無銘
- 素材:絹
- 技法:肉筆(墨画)
- 寸法:約93×約65cm
- 所蔵:いわき絵のぼり吉田
江戸の「厄除け」を担った素朴な図像
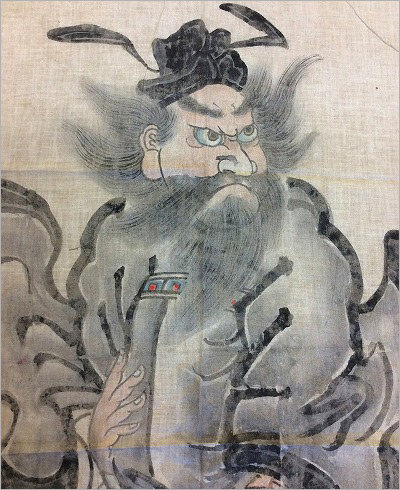
—— 本作は、絹地に墨で描かれた鍾馗(しょうき)像の幟です。
鍾馗は 疫病除け・学業成就の守護として広く信じられ、端午の節句や町場の祈りの場で掲げられました。
本作は江戸時代の神社で用いられていたとも伝え聞きます。
署名はなく作者不詳ですが、生活の中で機能する「実用絵画」として用いられた幟ならではの、
端正すぎない筆致の中に、手向けの心と祈りの熱が息づいています。
いわゆる名工の作だけでなく、地域の人々が自ら描いた例も少なくありません。
素朴であっても、 見飽きない魅力があるのは、暮らしと信仰に密着した用の美の現れと言えるでしょう。
古布流通に残る「スタンプ」の痕跡

—— 江戸期の絵のぼりには、外国風のスタンプが押された個体が稀に見られます。
これは、近代以降に古布として再流通した際の管理印・仕分け印と考えられ、 時に布地として転用され市場に出た痕跡でもあります。
優れた幟にも押印例が確認され、 その過程で多くの作例が散逸した可能性も否定できません。
だからこそ、こうした素朴な一幅にも、暮らしの手触りと
地域信仰の記憶が確かに宿ります。
過去の生活の証言として適切に保存し、「文化の還元」——学びを未来へ返す営みにつなげていきたいと考えています。
いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇 (しんしょう)
他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧ください
- ホーム>
- 職人について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- 無銘|鍾馗図幟
バナースペース
 SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
松重豊さん出演「福島豊」Youtubeシリーズにて、
絵のぼり工房として紹介されています。
工房訪問回および絵のぼりのお披露目回です。
人の集まるハレの場を象徴する、ユーモラスな「旗印」として。
松重豊さんが工房へ(第7話)
絵のぼりお披露目(第8話)




