- ホーム>
- 職人について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- セーマンドーマン刺繍入り|鍾馗図幟
鍾馗図幟(四半旗)|セーマンドーマン刺繍
——明治~大正期、東日本に息づいた魔除けの祈り
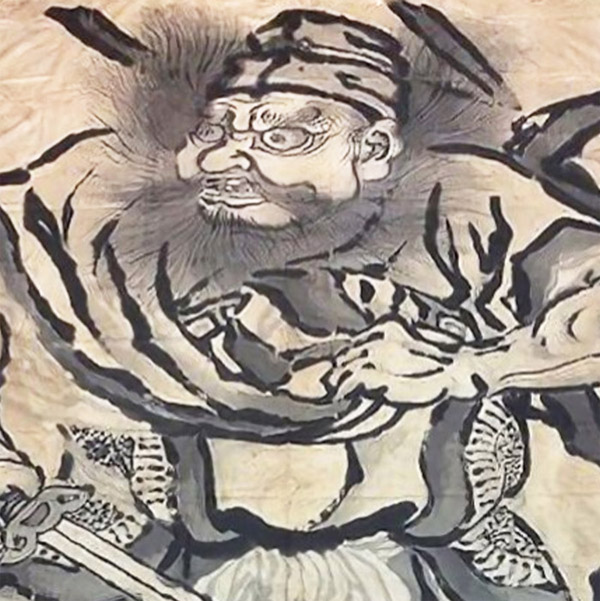
作品情報

- 題名:鍾馗図幟(四半旗) ※非売品
- 時代:明治~大正
- 産地:東日本(推定)
- 作者:無銘
- 素材:木綿(推定)
- 技法:肉筆(手描き)
- 寸法:約330×約190cm
- 特徴:乳(ち)にセーマンドーマン刺繍
- 所蔵:いわき絵のぼり吉田
—— 男児の健やかな成長と魔除けを願う鍾馗(しょうき)の図。
本作は細長い幟ではなく幅広の「四半旗」形式で、室外に掲げても強い存在感を放つ大画面です。
四半旗の風格と制作年代の手がかり

—— 四半旗は、戦国の旗指物にも通じる古風な造形が魅力です。
ただし本作にはミシン縫製が確認でき、意匠は古雅でも明治後期~大正期の制作と判断できます。
鍾馗幟の分布——東日本に根づく信仰圏
—— 鍾馗幟は関東周辺を中心に多く流通しました(四国・九州では比較的少数)。
本作に落款は無いものの、図様・刺繍・慣習から東日本の風土が色濃く反映されていると考えられます。
セーマンドーマン——乳に宿る魔除けの刺繍
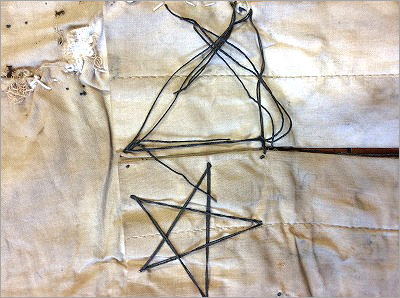
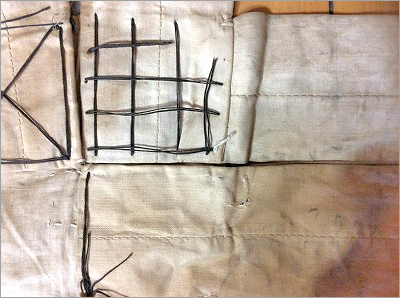
—— 竿通しの乳(ち)や紐飾りに施されたセーマンドーマンは、江戸期以前から伝わる魔除けのまじない。
子どもの着物や旗指物にも見られる「祈りの刺繍文化」が、明治・大正期にも脈々と受け継がれていました。
祈りを纏う大画面——生活と信仰が重なる幟
—— 四半旗という古風な姿と、ミシン縫製が示す近代の気配。
その交点に、地域の暮らしと節句の祈りが息づいています。
いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇(しんしょう)
他の江戸期・近代の絵のぼりも、以下からご覧ください
- ホーム>
- 職人について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- セーマンドーマン刺繍入り|鍾馗図幟
バナースペース
 SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):
「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」





