- ホーム>
- 職人について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- 須藤晏斎|岩戸神楽乃起顕図幟
須藤晏斎(幕末の町絵師)|岩戸神楽乃起顕図幟
——庶民信仰と祝祭芸能としての神話図像

江戸の「実用絵画」を現代へ——文化の還元としての収集と再発見
—— いわき絵のぼりの絵師・辰昇(しんしょう)です。
江戸時代の肉筆絵のぼりを収集・研究し、 その筆法・構図・色を現代の旗印に再構築する制作を行っています。
本頁では、幕末から明治初期にかけ栃木・佐野で活躍した町絵師須藤晏斎(あんさい)による
『岩戸神楽乃起顕図幟』をご紹介します。
祝祭の場で“演じられる神話”を描いた節句幟(絵のぼり)で、 庶民信仰と芸能が交差する、まさに「祭礼絵画」の好例です。
- 題名:岩戸神楽乃起顕図幟 ※非売品
- 絵師:須藤晏斎(すどうあんさい)
- 制作年代:幕末
- 寸法:縦 約440cm × 横 約43cm
- 素材:木綿地・墨・顔料
- 技法:肉筆(手描き)
- 所蔵:いわき絵のぼり吉田
祝祭の舞台を描く──「神楽の神話」へのまなざし
—— 本作は、天照大神の“岩戸隠れ”と“再顕”の神話を、神楽演目として表した場面構成が特徴です。
浮世絵や芝居に通じる演劇性・人物配置・運動感が前面に出ており、
祝祭空間における「登場神」としての描写が意識されています。
明治以降に見られる神聖性重視の図像とは異なり、江戸の庶民感覚に根ざした
“演じられる神々”の造形がここにあります。
作者・須藤晏斎──町絵師の仕事と筆致
—— 晏斎は佐野の出身で、各地の絵のぼり・絵馬の制作に携わりました。
同時代の版画や肉筆と響き合う力強い線と、祝祭画にふさわしい躍動感が特徴です。
実用品としての性質上、短納期や屋外掲揚を前提とするために、制作上の粗さが残る箇所もありますが、
それは当時の制作事情の反映であり、他作に見られる緻密な構成や確かな画力が 晏斎の並外れた実力を裏づけています。

当時の図像様式としての「簡素化」
—— 天照大神像は記号性が高く簡略に描かれています。
これは個々の画家の力量ではなく、 神楽という祝祭演目を描く江戸後期の絵画に共通する傾向でした。
同時期の絵馬でも、天照大神が簡素に描かれる例が多くみられます。

・天鈿女命──舞の神。晒し舞台のような所作で場を盛り上げる。
・猿田彦命──導きの神。長い鼻の造形で寓意を担う。

・天手力男命──力動の神。岩戸を押し開くダイナミックな構図で、画面の焦点を作る。
雅号印と真贋の手がかり
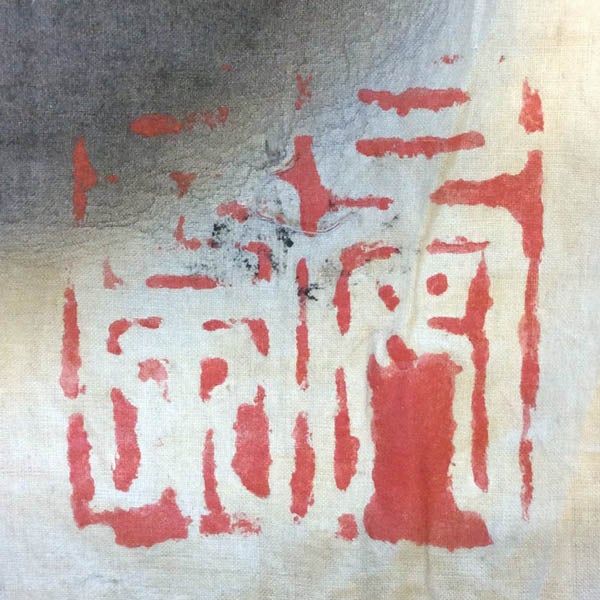
—— 画面下部に晏斎の雅号印を確認。
落款・筆線・顔料運用などの要素によって、須藤晏斎の実作として位置づけられます。
父・晏斎と子・鞆音——江戸から明治への表現の分岐
—— 晏斎は庶民の祈りを描く町絵師。
対して実子である大和絵の第一人者・小堀鞆音は有職故実に基づく歴史画を確立し、 近代国家の公的美術を担いました。
この父子の対比は、江戸の祝祭文化から明治の制度化された歴史観へ
の転換を可視化します。
幕末の社会不安と「再顕」イメージ
—— 黒船来航や統治の動揺、飢饉・疫病が相次いだ幕末、岩戸開き=光の再来の物語は
広い階層の人びとの再生願望と重なりました。
初節句の幟にもその象徴性が求められ、 本作もまた祈りの可視化として掲げられた可能性があります。
なぜ「天岩戸図」ではなく「岩戸神楽乃起顕図幟」か
—— 本作は神話内容そのものではなく、同時代の浮世絵と同様に、神楽として演じられる場面が図像構成の元となっています。
したがって浮世絵と同系の作品名を冠するのが適切であり、「岩戸神楽乃起顕図幟」としました。
幟を依頼した人びと——家運隆昌の願い
—— 激動の幕末を生きる武家・富裕層は、光の再来の象徴に家運隆昌の祈りを託し、格式ある素材と
信頼の置ける筆を求めました。
その中でも、屋外掲揚に耐えうる節句幟(絵のぼり)は、家庭祭礼の中心的存在でした。
情報社会がもたらす「文化の集積」と再起動
—— 須藤晏斎は幕末における絵のぼりの名手であり、残された作品は非常に稀です。
にもかかわらず、本作との出会いはネットを介した、ごく近距離(同町内)からの入手でした。
物理的に近くとも、情報がなければ出会えない——現代の情報結節点が、文化の行方を左右します。
各地に点在していた絵のぼりが、視点のもとに再び集まり「文化の還元」として現代に息を吹き返す。
その蓄積と公開は、次代への共有資産づくりでもあります。
いわき絵のぼり吉田・絵師 辰昇 (しんしょう)
他の江戸期の絵のぼりは、以下をタップしてご覧ください
- ホーム>
- 職人について>
- 江戸期の絵のぼり収集記>
- 須藤晏斎|岩戸神楽乃起顕図幟
バナースペース
 SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
SNSでも日々情報を発信しています(X/Instagram)
工房をご見学いただいた方の投稿より(@irodori_koinbr 様):
「絵幟の歴史を堪能出来る空間でした。鍾馗幟旗は生で見ると迫力がヤバかったです。生で見なきゃもったいないです!」





